横浜スタジアム
CSではウィング席が巨人応援席となります📣 pic.twitter.com/sH1nckSafy— スポーツ報知 巨人取材班 (@hochi_giants) October 11, 2025
青に染まるハマスタのスタンド。
テレビ越しでもはっきり分かるほど、ホームの色が球場を包んでいます。歓声とチャントが渦を巻き、応援団の声がグラウンドへ押し寄せる一方で、巨人ファンの姿は点々としか見えません。
そんな光景を目にして、「巨人、かわいそう」とつぶやく声が上がるのも無理はないでしょう。
短期決戦のアウェイでは、席割りや動線、カメラのアングルなどが意外なほど影響し、選手の表情や試合の印象までも変わってしまいます。
現地でのざわめきやSNSでの反応、テレビ映像に映る“色の偏り”──これらが重なって生まれる空気を、具体的な事例とともに丁寧に掘り下げていきます。
この記事では、座席割りや音響の問題、過去の事例、そしてファンが現場でできる工夫まで、現場の臨場感を大切にしながら冷静に整理していきます。
ハマスタ巨人がかわいそう?CSで “涙”の理由と現場の空気
引用:https://sp.baystars.co.jp/news/2019/03/0314_06.php
セ・クライマックスシリーズ、横浜スタジアム(ハマスタ)での光景は一目で「ホーム一色」
。青いユニフォーム、青い旗、そして歓声——そんな中で巨人ファンの姿が極端に少なく見える場面が、SNSや解説席で「かわいそうだ」という声を呼んでいます。
解説を務めた佐々木主浩氏も「ちょっと、かわいそうな気がします」と同情を示し、球場の“圧”が話題になりました。
なぜ「かわいそう」に見えるのか
理由は大きく分けて2点。まずビジター応援席の扱いです。通常の外野応援エリアではなく、レフト外野の一部やウィング席に限定されるなど、観客の配置が変更され「巨人ファンが目立たない」状態になっています。これによりスタンドの視覚的な“ホーム偏り”が強まり、画面越しでも完全アウェーの印象が伝わります。
もう一つは声の大きさと密度。ホーム側の応援団・チャンテが球場全体に響く一方で、離れた小さなビジター席からは応援が届きにくく、選手・観客双方に孤立感が生まれやすい——こうした物理的条件が「かわいそう」という感想を生んでいます。現場の解説や映像でその温度差が繰り返し指摘されました。
現場メモ
| 観察ポイント | 状況(今回のCS) |
|---|---|
| ビジター席の位置 | レフト外野→ウィング等へ限定(視認性低下)。 |
| スタンドの色彩 | ホーム(青)優勢 → 画面映えで“完全アウェイ”印象に。 |
| 解説者の反応 | 同情的なコメントが散見(例:佐々木氏)。 |

次の項ではハマスタ特有の球場事情やCSのルール面が巨人にどのように影響するかをデータや過去事例を交えて掘り下げます。
ハマスタでの巨人戦:スタンド・空気・環境の影響

横浜スタジアム(ハマスタ)はコンパクトで観客が近く、ホームの一体感を作りやすい球場です。その特性がCSの舞台になると、ビジターチームにとって“視覚的・音響的なアウェイ感”を強める要因になります。実際に今季のCSでは、通常のレフト外野からビジター席の割り当てを変更し、ウィング(STAR SIDE)エリアへ移す運用が取られた例が報じられています。
ビジター席の割り当てと「見え方」の問題
ビジター専用エリアが外野の中心から離れると、映像で見る限りスタンド全体がホームカラーで占められて見えやすくなります。座席のパターン(HIGH/MIDDLE/LOW)でホーム外野の範囲が変わることを球団案内でも明示しており、試合ごとの配置で視認性が大きく変わるのが実情です。これにより「巨人ファンの姿が目立たない」との指摘が出ています。
声の届き方──音量と密度の差
ハマスタは応援が密集すると音が球場全体に回りやすく、逆にビジター席が小規模だと声が埋もれがちです。解説者やSNSでも「ちょっとかわいそう」といった同情的な反応が出ており、観客分布が選手の心理やテレビでの印象にまで影響を及ぼす様子が伺えます。
数値で見る“差”の指摘
有志の分析では、ハマスタのCS時におけるビジター席の割合やホーム/ビジター比が他球場と比べて偏っているとのデータも示されています。座席数そのものが絶対的に少ないかどうかは論点がありますが、比率で見たときの「視覚的な偏り」は無視できないと結論づけられています。
影響項目と具体例
| 影響項目 | 具体例 |
|---|---|
| 視認性 | ビジター席がウィングへ移動 → テレビ映像でホーム色が優勢。 |
| 音響 | 応援密度の差 → ビジターの声が届きにくい。 |
| 観客動線 | 席パターンによる配分の違い → HOME/MIDDLE/HIGHで範囲が変化。 |
球場の物理的な特徴と運営上の座席割りが組み合わさると、選手への“ホームの圧”や画面を通した印象は想像以上に強くなります。結果として「巨人かわいそう」と受け取られる場面が生まれやすく、現地の空気が競技結果以外の形でも試合の語られ方に影響を与える――それがハマスタという舞台の現実です。
CS 制度と舞台設定:巨人にとってのハードルとは

まず押さえておくべきは、クライマックスシリーズ(CS)の「仕組みそのもの」がホーム有利に設計されている点です。ファーストステージは「2位 vs 3位」の3試合制で、すべて2位球団の本拠地で行われます。ファイナルステージは1位球団とファーストステージ勝者の“6試合制”(実質は先に4勝)で、リーグ優勝チームにはあらかじめ1勝のアドバンテージが与えられ、すべての試合が1位球団の本拠地で行われます。これらはNPBの公式運用です。
1勝アドバンテージがもたらす“数値的ハンデ”
優勝チームは初めから1勝を持った状態で始まるため、挑戦側は「4勝」が必要、優勝側は実質「3勝」で決まります。短期決戦での1勝差は確率論的にも大きく、先発ローテーションやブルペン配分、采配の余裕に直結します。制度自体への賛否も根強く、メディアやファンの間で議論が続いています。
「全試合ホーム開催」が持つ現場面の優位性
「すべての試合が上位の本拠地で行われる」ことは、単に慣れたフィールドで戦えるという以上の意味を持ちます。スタンドの色彩、応援の密度、ベンチ裏の動線、打者の視界(背景)といった“球場固有の要素”が有利側に働きやすく、短期決戦ほどその差は顕著になります。さらに、球団ごとの座席割りやイベント運用によってはビジターファンの視認性や応援音量が制限され、「完全アウェイ」状態を作り出すケースもあることが指摘されています。
ハマスタ(横浜)という舞台が重ねる“二重のハードル”
特定球場の事情が加わると、巨人側のハードルはさらに高まります。ハマスタのCS開催に際してはビジター席の配置・数が話題になっており、座席比率や位置の関係で“視覚的にホームが圧倒する”という分析も出ています。数値的には(球場全体に占める)ビジター用の割合が小さいとの指摘があり、これがテレビ映像や現地の空気感にまで影響を及ぼします。
制度 × 舞台 が生む主なハードル
| ハードル | 具体的な影響 |
|---|---|
| 1勝アドバンテージ | 挑戦側は実質的に1勝多く必要。短期戦での確率的不利。 |
| 全試合ホーム開催 | 応援・音圧・視界など複合的にホーム有利。戦術・采配に余裕が生じる。 |
| 球場ごとの座席運用 | ビジター席の位置・数で「見え方」「声の届き方」が変わる(ハマスタ事例)。 |

制度設計(1勝アドバンテージ+全試合ホーム)と、球場ごとの運用(ビジター席の割り当てやスタンドの特性)が重なると、巨人のような“人気・動員の大きい”球団でも、短期決戦の舞台では意外なほど不利な立場に立たされることがあります。
過去事例に見る「泣き所」:他球団や過去巨人の苦闘
クライマックスシリーズは短期決戦ゆえ「会場による影響」が結果に直結しやすい。実際、巨人は2016年のファーストステージで横浜(ハマスタ)に敗退し、延長の末にシリーズ敗退を喫している。この年の最終戦は延長11回のサヨナラで決着がつき、劇的な敗戦は会場の雰囲気も含め語り草になった。
最近でも、ハマスタでのビジター席設定が話題になり「全面青一色」とSNSで注目された事例がある。左翼席がホーム指定となり、巨人ファンがウイング席へ限定される運用があったため、画面越しの“完全アウェー感”が批判を呼んだ。
他球場の例も参考になる。広島・マツダスタジアムでは“ビジターパフォーマンス席”の配置や集客動員策が強烈なホーム空気を作り、過去にビジターが圧倒される場面が複数報告されている(いわゆる「ビジパフォの呪い」など)。これらは単なる色彩の問題にとどまらず、声の届き方や視界(打者の背景)にも影響を与える。
座席数・比率を定量分析した指摘もある。ハマスタは球場規模の制約からビジター割り当てが相対的に小さく見えることがあり、比率で見ると他球場と比べ偏りが生じやすいとの分析が出ている。短期決戦で「見た目のアドバンテージ」がファン心理・選手心理に与える影響は無視できない。
代表的な“泣き所”事例
| 年 | 対戦 | 会場 | 主要な泣き所 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 巨人 vs DeNA | ハマスタ | 延長の末にファーストステージ敗退(会場の雰囲気が注目)。 |
| 2015 | DeNA vs 広島(例) | マツダ | ビジターパフォ席でホーム色が強く、ビジターが押される事象。 |
| 2025 | 巨人 vs DeNA(CS) | ハマスタ | 左翼をホーム指定にして「全面青」化、批判が噴出。 |
これらの事例は「制度(全試合ホーム開催や短期決戦)」と「実際の球場運用(席割り・集客施策)」が重なったときに顕在化する。結果として生まれる“泣き所”は勝敗だけでなく、ファンの語り方やメディア論調にも波及しており、ポストシーズン特有の緊張感をさらに高めている。
巨人に贈る“応援案”?ファンができること・期待される変化
ハマスタのようにビジター席が限定される状況でも、工夫次第で選手に届く応援は可能です。まず現実を押さえると、今季のCSでは外野をホーム専用にし、ビジターをウィング席に限定する運用が実際に取られ話題になりました(批判も出ています)。チケット情報や座席種別も公式に出ているので、事前把握が第一歩です。
事前準備(チケット・集合)
・公式ファンクラブ先行や連番抽選でウィング席や内野の確保を狙う(球団先行枠の案内をこまめにチェック)。
・現地での合流ポイント(駅・コンコース)を決め、まとまって入場することで視覚的インパクトを作る。公式ガイドでウィングの扱い(内野同様の観戦ルール)も確認しておくと安心です。
当日の応援の工夫
・声が届きにくい分、視覚的要素(小さな旗、統一ユニフォーム、肩章型の応援グッズ)で存在感を出す。
・カメラ映えするようSNSでの事前告知(ハッシュタグの統一、集合写真の投稿)を行い、画面越しの「青一色」に対抗する手法も有効です。SNS上での世論形成は、球団の座席運用に対する批判や改善要求につながることがあります(実際に今回もSNSで議論が湧きました)。
ファンとしての窓口活動
・「ビジター応援デー」やファンクラブの来場登録を活用し、来場数や応援の正当性を示す。球団に対する要望提出やアンケート回答で改善を促すのも一手です(過去にビジター応援デーを開催した例あり)。
まとめ
| やること | 期待効果 |
|---|---|
| 先行抽選でまとまった席を確保 | 現地での視覚的存在感確保 |
| 統一ハッシュタグでSNS拡散 | テレビ・ネット上の印象を変える |
| ファンクラブ来場登録や要望提出 | 球団運用へのプレッシャー形成 |

作戦は「規則内で目立つ」「現地でまとまる」「ネットで声を大きくする」の三本柱。短期決戦ほど一体感は選手の力になります。まとまった動きが増えれば、運営側の対応も変わり得ます — まずは安全かつマナーを守って、一致団結で後押ししましょう。
![]()
自宅で好きな時間に全試合観戦できるから、応援がもっと楽しく、毎日の野球ニュースもよりワクワクします!
>>野球見るなら、スカパー!プロ野球セット![]()
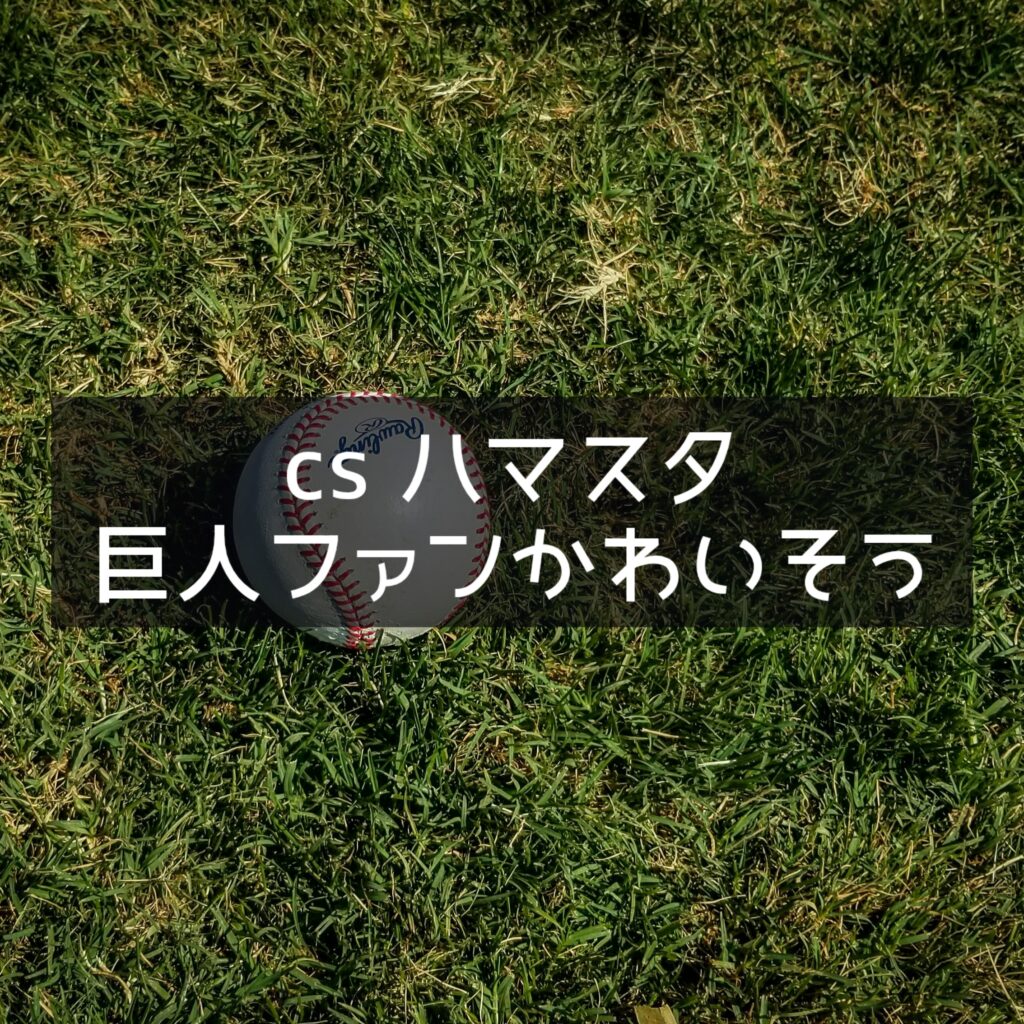



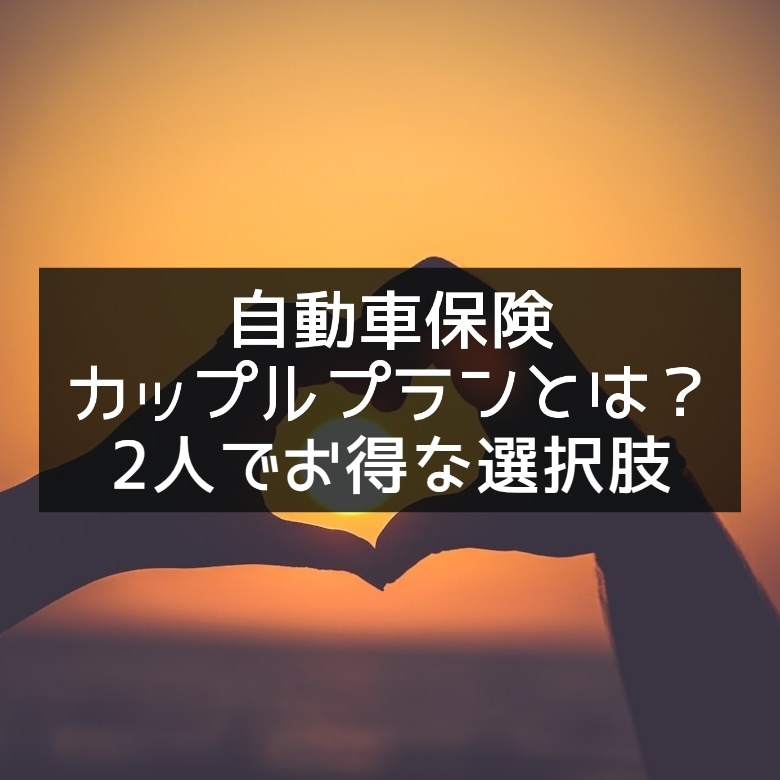
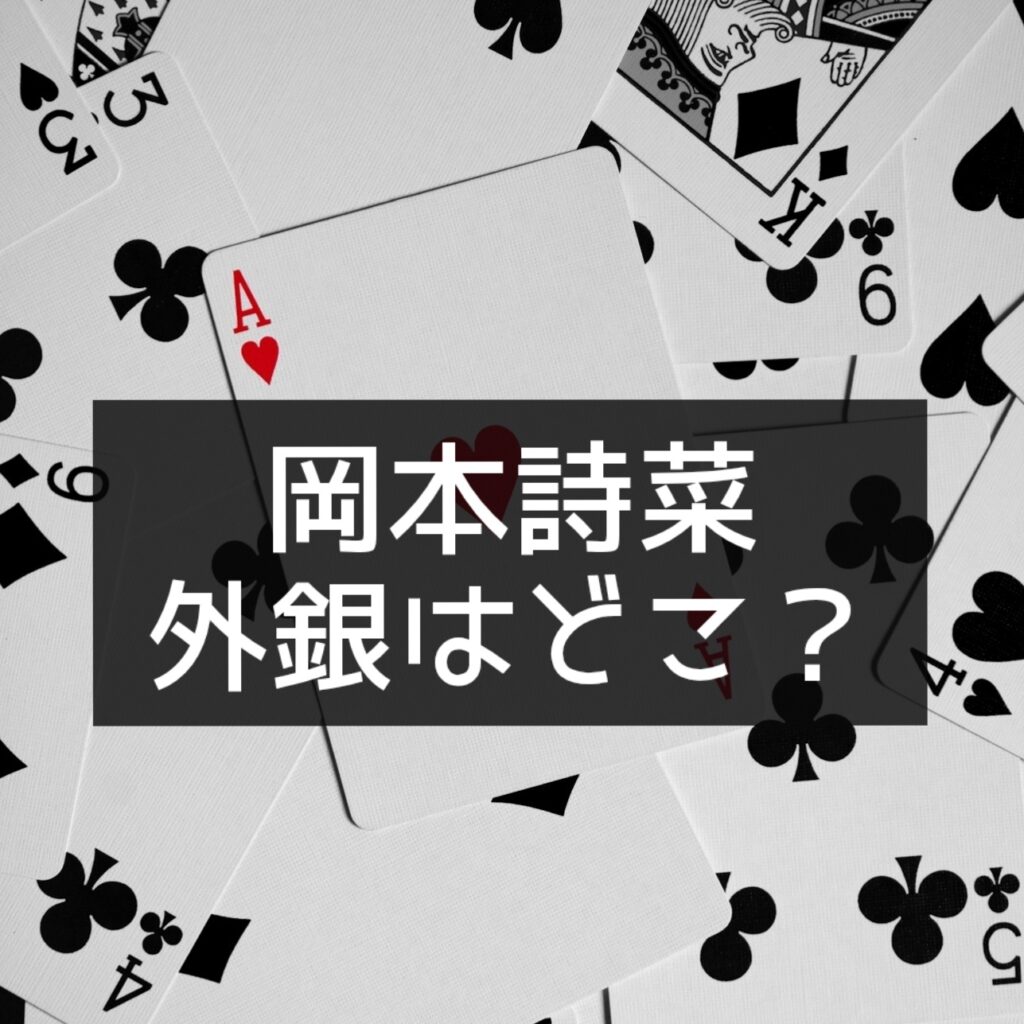
コメント